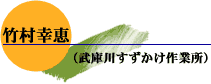 |
|
|
幸恵さんも、そんな「できない」時間を、くぐり抜けてきた。なにか「できる」ことはないかと、家族ともども焦った。ひとつ「できる」ことがあれば、次のステップヘ進める。そんな幸恵さんのファーストステップは、高校への自力通学だった。とても自信がついた。 やがてすずかけ作業所屋外作業班で働く彼女の前に、次なるステップが現れた。それが絵画だった。しかもこのステップは、克服したり頑張らなくてもいい、他の人と比較もされない、全く自由なステップだった。彼女が、すずかけ作業所の絵画クラブで、初めて絵の具を使ったときのことをはたよしこさんはこう書いている。 最初の一筆。恐る恐るの緊張した顔が見る見る溶けて、満面の笑顔が流れだした。色と色とが混ざり合い滲み合って、新しい色を生む。その瞬間の小さなドラマが、彼女のこころの何かと共鳴したのだろう。彼女は、ゆっくりと筆を引いて、そのドラマのステージを、自力で広げていく。その喜び、その快感。彼女は少し興奮して、ウーウーと言いながら、飽くことなく色の線を引き続けた。 幸恵さんが「できる」「できない」の世界から解放された瞬間だ。解放され、無心になって絵画へ没入していく。絵が自分なのか、自分が絵なのか、分からなくなる。はたさんの言葉を借りれば、小さくて壮大な自己内宇宙での対話遊戯を、彼女は始めた。 絵の具がしたたり落ちる様を、うっとり眺めている彼女を見ると、この星に重力があることを、感謝したくなる。 |
||
 障害を持った人にとって、「できる」「できない」からの解放ほど困難なことはない。同じ年齢の人と比較され、「できない」ことばかりが注目され、負なる存在としての自己のみが成長してしまう。学校は、「できない」事実をさんざん確認させられる場所で、生きる楽しさからは、何万キロも離れた社会になってしまう。
障害を持った人にとって、「できる」「できない」からの解放ほど困難なことはない。同じ年齢の人と比較され、「できない」ことばかりが注目され、負なる存在としての自己のみが成長してしまう。学校は、「できない」事実をさんざん確認させられる場所で、生きる楽しさからは、何万キロも離れた社会になってしまう。