|
|
 |
|
|
 |
 |
東京に住む多くの人と同じように、9月11日の同時多発テロを、僕は、悲しみと恐れと怒りの入り交じった気持ちで受け止めた。その思いは、テレビ中継が被害者の増加を報じるにしたがって深くなった。しかしそれから数日、数週間とたつうちに、当初の強烈な実感は、いらだたしい距離感と葛藤を始めた。ブッシュ政権が独善的で盲目的な愛国心をもって反応し、抑制のきかない軍事力行使につながるに及んで、そうした感覚はいっそう強まった。
アメリカ人の95パーセント、そしてオピニオン・リーダーの100パーセントが軍事的な制裁を支持していると聞いて、僕は驚いた。残り5パーセントのうちの一人として、寂しく、むなしい気分だった。僕たちは15年にわたるベトナムでの戦いから何も学ばなかったのだろうか。この動きにストップをかけ、軍事力に訴えることがほんとうにテロに対する答えなのだろうかと、疑問を提示する人はいないのか。
まもなく登場したのが、ノーム・チョムスキーの著書『9.11』だった。この1冊に救われた人間がどれほどいただろう。歴史を知り、恐れずに教訓を引き出そうとする人間がいた。マスメディアや政治システムの助けを借りない、自由の声である。彼の主張は、あらゆる暴力と対峙する。それが強国による軍事介入であろうと、その裏側で「権利を奪われた」と主張する人々による残忍なテロであろうと。
プロデューサーの山上と僕は、彼の主張を伝えるべきだと考えた。そして2001年の末、チョムスキーに接触し、2、3か月以内に3回のインタビューを受けてほしいと依頼した。僕たちはそれらのインタビューと、彼の日常生活のいくつかのシーンをつなげて、映画をつくりたいと考えていた。
翌日、チョムスキーからEメールで返事が届いた。映画の企画は支持するが、実現はむずかしいという内容だった。インタビューの時間がとれるとしても、何ヶ月後かに、オフィスで1回だけだろう。しかし、今後数ヶ月の間に何度も講演を行なうことになっているので、それを撮影するのはかまわないという。僕たちは、いくつかの講演を撮影し、長いインタビューを1回行なうことで同意した。しかし、公的な活動風景を撮るだけで「チョムスキーその人」を描き切れるのかどうか心配だった。
やがて僕たちは、それこそが「チョムスキーその人」であることを知った。チョムスキーは語る――人々に語ることこそが彼の日常生活であり、人生を通じて絶え間なく行なってきたことなのだ。
大きな講演や海外講演ツアーは何年も前から決まるが、時間が許すかぎり、町のホールや大学での小さな講演が、タイトなスケジュールの隙間にぎっしり詰め込まれていく。さらに、9月11日のテロの後、1年の間に彼は数百ものインタビューを受けている。
「チョムスキー効果」と呼ばれる現象があることも知った。彼の講演に参加した人たちは、自分が長い間、心に抱いていたけれど口にできなかった懸念について彼が語るのを聞いて、励まされる。
チョムスキーは何年も前に、自分の役割を意識的に選択したに違いない。世界をほんとうに変えようとする人たちに、事実と分析を、自分の口で、直接、伝えていこうと。それは、政治的な変革は地域コミュニティを基盤とする大衆社会のレベルで実現されるという、彼の信念の具現化である。
語ることが、チョムスキー自身にも驚くべき効果をもたらすという事実を、僕たちは目撃した。2002年3月、サンフランシスコ周辺で過ごした、きわめて多忙な週だった。
彼はカリフォルニア大学バークレー校から、言語学のレクチャーを2回行なうために招かれていた。だから彼は大学で、周辺の大学の言語学の学生や教授たちとの面談や会合を重ねた。そして「自由時間」を利用して、5日間で5回の講演を行なったのである(僕たちはそのうちの3回を撮影した)。聴衆は合わせて5000人にのぼった。
金曜日にパロアルトで最後の講演が行なわれる頃には、彼は疲れ切り、声はかすれていた。しかしホテルの会場で1000人の熱心な人々を前に語り始めると、とたんにエネルギーを回復した。そして、宇宙の軍備化に関する長い話から始まった講演は、夜が更けるまで続いた。彼の講演では、最後に行なわれる質疑応答がそのまま10分前後のミニ講演となることが珍しくない。
講演が終了した後も、なかなかそばを離れようとしないグループからの質問に忍耐強く答えながら、チョムスキーはさらに45分を過ごした。サインを書き過ぎて指がひきつり、「もう書けないよ」と本人が笑うほどだった。チョムスキーは疲れ知らずではあるが、けっして鉄人ではない。しかしその彼は、会場を出るときにもまだ話していた。最近、訪れたトルコのクルド民族地域で励まされたことを、友人に語っていたのだ。
制作期間中、この映画の仮タイトルは『Chomsky Talks――チョムスキーは語る』だった。僕たちはその控えめな感じと単純さを気に入っていた。どちらも、チョムスキーを特徴づける性質である。
彼の運動は語ることだ。自他ともに認めるように、彼は語るだけである。後の判断は聴衆の手に委ねられている。私たちは、この映画もそういう映画にしたかった。ナレーションはつけない。ただチョムスキーが自分の考えを語り、問いを投げかけるだけ。答えは、大衆と政治的な舞台が決めることである。
この映画のなかでチョムスキーは、僕たちが直視すべき問題を提示している。そして、僕たちの当初の心配に反してこの映画は、彼の機知や、温かさや、ゆるぎない信念とともに、チョムスキーその人をも描き出すことができたと思っている。
 |
 |
 |
|
ジャン・ユンカ-マン 2002年夏 |
|
|
|
|
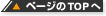 |
|
 |
|